道迷い対策と緊急時の行動方法について、私の体験と持っていて欲しいグッズもご紹介します。
山の中は、整備されて道標がしっかりある場所と、分かりにくいのに道標もピンクリボンも無い場所があります。
そんな所を歩いていると、ふっとした気の緩みから、遭難に繋がってしまうことも。
特に、山慣れしていない初心者に、多く発生しているので、しっかりした知識が必要です。
この記事では、想定外のことが起きた場合にどうするか、などについて解説します。
道迷いとは
読んで字のごとく、『道が分からなくなってしまったこと』です
ニュースなどでは、道に迷って遭難した人が・・・とか言ってますよね
でも道に迷った=遭難、では無いことも理解しておきましょう。
道迷いと遭難の違い。
遭難とは、道迷いを起こした後に正規ルートに戻れなくなってしまった
転倒・病気・滑落・転落などによって、自力で下山できない時
こんな風に、捉えてください。
なので道迷いをしても、自力で怪我も無く正規ルートに戻れたら、遭難とは言いません。
道迷いの主な原因
1番多いのが、道標の見落とし・見間違いです。
お喋りや花の写真を撮るなどに気が向いてしまって、道標があったことに気づけなかったり。
似たような文字や、東と西などを見間違える。
または、踏み跡があったから、そこへ入ってしまった。
さらには、紙地図もスマホの地図も持たずに、山へ入ったから道が分からなくなってしまう。
そして天候の変化により、視界が悪くなった事での道迷いも起きています。

道迷いしないための準備と予防策
では、どうしたら、このミスを回避することが出来るのか。
やはり登山には、知識が重要ということです。
事前のルート確認と計画
この山に登ろう!と決めたら、その山の情報を出来るだけ多く集めてください。
地図を見て、ルートや危険個所を把握したり、同じ山へ行った人の記事を何人分も読むことです。
どんな登山道の山なのかを、頭に思い浮かべられるくらい、把握しておくのがベストですね。
地図とコンパスの基本的な使い方
地図は登山の必需品・・・という記事で詳しく解説しているので、そちらも参考にして頂きたいです。
紙地図を完全に理解するには、有識者から『地図読み』を学ぶ必要があります。
しかし、コンパスを持っていて方角が分かれば、紙地図でも今自分が向いている方角くらいは分かります。
GPSデバイスやアプリの活用
また、スマホアプリの地図なら、紙飛行機マークや電気を照らすかのように、自分の位置が表示されます。
なので、分かりにくい所は数m移動してみると、正しいのか間違っているのかも分かるのです
下の画像は、左がヤマレコで右がYAMAPです。
かすかな記憶ですが(笑)、右の地図は黒斑山へ行った時の物でしょう。

標識や目印の確認方法
登山道に道標や目印になる物があったら、必ず写真を撮っておきましょう。
理由は、何時にそこを通過したか、が記録されるからです。
また、もし間違ったかも?と感じた時に、その写真を見て確認することも出来るからです。
さらに、道標がある所では必ず、地図を広げて位置を確認してください。
紙地図もスマホアプリ地図も、どちらも確認することで、地図を見ることに慣れていきます。

登山道の目印
その多くは、ピンク・赤・白い紐が木に付いている、のが登山道の目印です
ただし気を付けるべき点は、林業の人が付けた紐です。
色は登山道表示と同じ、ピンク・赤・白などが使われています。
「え?!あんな方にピンクがあるけど・・・」ってドキッとした時は、周辺を広く見渡してください。
林業の人の目印は、あっちにあったり、こっちにあったり・・・、道のように並んで無いことが多いです。
でも、これも場所によっては、本当に見分けがつかないこともあるので、やはりスマホ地図はあった方が良いですね
道に迷った時の対処方法
注意していても、道迷いが起きてしまったら・・・
対策方法を知っていれば、落ち着いて行動することが出来るので、しっかり覚えておいてください。
冷静に判断する
道に迷ったことに気が付いた瞬間、冷静さを失うことがほとんどです。
そんな時は、慌てて歩き回らずに、まずは立ち止まって飲み物を飲んだり、行動食を取るなどして気持ちを落ち着かせましょう
落ち着いたら、周りをしっかり見渡してください。
登山道らしきものは見えないか?
目印の赤やピンクの紐は見えないか?
歩いて来た道は、戻って行かれそうか?
その場を動かずに位置を確認する
スマホ地図を使っていたら、正規ルートからどれ位はなれているのか?を見てください。
その時、自分の体の向きを変えてみて、どっちの方角を向いているかも確認します。
紙地図の場合は、道標や目印の所で撮った写真を見ながら、今の時間と見比べコンパスで方角を調べ、おおよそ自分がいる場所を
見つけましょう。
この時に必要となるのが、自分の歩くスピードですが、このことに関しては地図は登山の必需品の中で、7-2に記載しています
周囲の地形や環境を把握する
周りを見渡したら、自分が尾根近くに居るのか、谷にいるのかを確認しましょう。
下の画像で、白い線は尾根や高い所で、青い線は谷や低い所です。
地図には、コースタイムも書かれているので、おおよその場所を把握することが出来ます。

決してやってはいけない事
自分の位置が把握できて無かったり、目印の紐などが全く見えない状態の場合、絶対にやってはいけないことがあります。
それは、「こっちの方へ行けば、登山道に出られるはずだ」と、確実な根拠も無いのに進んでしまうことです。
この考え方が、1番危険だという事を知っておいてください。
登山道に出られたらラッキーですが、出られなければ分からない場所を彷徨うことになります。
そんなことをしていると、体力を消耗して歩けなくなってしまうからです。(歩けなくなったら遭難)
来た道を戻る
もし歩いて来た所が分かるのであれば、登山道だと確認できる場所まで戻ってください。
引き返す時は特に、踏み跡や周りの景色に意識を向けて、さっき見た景色があるかどうか、など記憶を辿りながら歩きます。
そして登山に戻れたら、再び道迷いにはまらないよう、間違えた理由をしっかり考えてください。

道迷いした経験
私も道迷いしたことが何度かあります。^^;
でも原則の、来た道を戻るを行ったら、間違えた個所を見つけることが出来ました。
私の体験談①
下の画像の場所ではありませんが、これと同じようなものがある所で、ミスを犯したことが原因でした。
これは、道迷いを防ぐために置かれた、通行止めの目印です。
誰が行っているのかは分かりませんが、踏み跡がある所に数本の細い枝が並べて置いてありますね。
明らかに、人工的に置かれた枝や木などです。
私は、お喋りをしたり他の風景に気を取られていて、気が付かずにまたいで進んでしまったのです。

私の体験談②
それは、大雪の後でした。
雪山の経験をしようと、無雪期に5回以上歩いていて、良く知っている山に登りました。
迷ったのは下山時で、家が見える所まで降りて来たときでした。
谷間に入ったとき、雪が多くて少し低いとしか感じず、見覚えのある場所とは、かけ離れていたのです。
私には「ここへ出たら、少し下って左だったよね」、と記憶があったのですが、主人は見た目が違い過ぎて分からないと。
でも歩いて来た道と地図を見ると、ここへ出ることに間違いはありませんでした。
何度も登ったり下ったり
雪が多く無いところまで登り返し、上から眺めて登山道を探しましたが、3年前に歩いた時の記憶と繋がりませんでした。
「このまま下って行けば出られるじゃない?」と、言った私を止めたのは主人でした。
「かなり遠いから、道が繋がって無くて崖に出たら大変だよ!」と。
少し下りながら、両側の斜面に登山道が無いかを探したけど確信が持てなかったのです。
膝くらいまで積もった雪の中を、登っては下り3回くらい行っていたら、私はクタクタになってしまいました。
自分は、あと10分くらいで下山出来る位置にいる、という事は分かっていたけど、登山道が見つからなかったんです。
休憩したら目印を見つけた
私の様子を見た主人が、「日暮れまでまだ時間があるから休憩しよう」と言いました。
倒木に座って、「なんでここで道が分からないんだろう?」と、お菓子を食べながら話し、ゆっくりと辺りを見回しました。
すると、クネクネ伸びた木の枝の間に、火事注意という看板を見つけたのです。
3回も往復している時には、全く見えなかったので、すごく不思議な気分でした。
冷静になることの重要性
必死に探している時は、全く目につかなかったのに、座って話しながら見回したら、見つかった人工物。
この看板があるのは、登山道の印です。
そこで、その看板に近づいて周りを見たら、直ぐに登山道が見つかりました!
あんなに周りを見ながら、上り下りをしていたのに・・・・・
自分では落ち着いているつもりだったのですが、「なんで?」と疲れとで冷静さを失っていたんですね。
遭難した場合の対処方法
道迷いから正規の登山道に戻れなくなった場合、自力で歩いて下山できなかった場合、を遭難と言います
ここでは、怪我や病気で行動不能になった場合では無く、道迷いからの遭難についてお話します。
沢や川に降りてはいけない理由
水は下へ流れて行ってるので、辿って行けば下山できると思いがちですが、これは絶対に行ってはダメな行動です。
その理由は、下って行った時に崖・滝・堤防などにぶつかってしまうと、左右の斜面は急なことが多く、登り返せなくなってしま
うからです。
そんなところを無理に登ったり、川を下り続けて転落し死亡してしまう事故は、毎年起きていることなんですよ。
登ることの重要性
道に迷い、どうしても登山道が見つけられない場合は、登れそうなところを見つけて上を目指しましょう。
この時、危険な斜面は避けてくださいね、落ちる・滑るなどで足を痛めたら、歩けなくなるからです。
登りはじめならまだしも、下山中となると疲れているから、登り返すことは大変だと諦めないでください!
山並みを見れば分かるように、下って行っても人家のある所へ出られるとは限りません。
でも上に登って行けば、必ずそれ以上登れない場所に出ますよね。
山頂であったり尾根道であったり。
助かる可能性が大きい
山頂や尾根道には、登山道が通っていることが多いのも、知っての通りです。
さらに、高い場所からは周りの景色が見えやすく、地形を把握しやすくなります。
それは地図やコンパスを使って、自分の位置を把握しやすいということです。
また、そういう場所にいる方が、捜索隊が来た時にも見えやすくて発見されやすいのです。
緊急連絡先と救助要請の方法
山に入るときには、必ず登山届を提出してください。
登山ポストに出すのは個人情報が心配だという方は、登る山の警察や使っているスマホ地図で出しても良いでのす。
また、家族や知人・職場の人など、親しい人にも同じように登山計画書を渡してください。これはメールでもOK。
〇山へ〇〇登山口から登って〇〇へ下山、予定時刻は〇〇時だから、〇〇時になても連絡が無かったら捜索願を出してほしい。
このように伝えておきましょう。
自分では連絡できない
山の中は電波が届いて無い場所が多く、まして登山道から外れた場合、自分では救助要請が出せないと思ってください。
またココヘリなどの山岳救助機関へ加入していて、発信機を持っていたとしても、救助要請が出されなければ捜索は始まりません
必ず、登山届は親しい人にも出してください。
ビバークの準備
もし日が暮れるまでに、下山できないとなった場合は、辺りが良く見える明るさの内にビバークの準備を整えてください。
ビバークとは、予定外に山中で一夜を過ごすことです。
こういう、もしもの時のために食料や飲料を多めに持ち、保温着やレインウェアも必ずザックに入れておく必要があるのです
またスマホの充電器を持つことも忘れないでください。
スマホは漆黒の山中で、気を紛らすことが出来るしライトが点くし、翌日に行動する場合にも必要だから。
ビバークに適した場所
適した場所は、眠ってしまっても滑落の心配が無い広いところです。
そして一夜を過ごすことになるので、岩がゴツゴツしていない、枝が多く落ちていないなどの快適性を保てる場所を探しましょう
また、樹林帯の中の方が風や雨を避けられるので良いです。
どう過ごすか
出来るだけ身体を冷やさないように、落ち葉があったら集めて敷き、着れるウェアを全て着ます。
夏でも山の中の夜は、気温が低くなるから、低体温症になるのを避けるためです。
食べ物はザックの中に入れて、匂いで動物が寄ってくるのを防ぎます。
ヘッドライトは、首から下げて直ぐに使えるように。
ピクニックシートや山座布団を敷いて、座っても下から冷えないようにします。
バーナーを持っていたら、火事に気を付けながら火を点け、飲み物を温めて飲むのも、気持ちが落ち着くから良いです。
遭難対策グッズ
たとえ短時間の低山だとしても、何が起こるか分からないのが、山の中です
何かあった時のことを想定して、対応できるものをザックに入れておいてください。
遭難した時に必要なもの
山の夜は冷え込みます。
体を冷やしてしまうと低体温症になって、命を落としてしまうので体を温めること、を1番に考えてください。
その為には、ツエルトや保温着、座る時に使う座布団などが必要です。
温かい食べ物や飲み物を、口にすることが出来ない状況がほとんどだと思うので、とにかく冷やさない事です!
ツエルト(テント型)
ツエルトと言って、超軽量の簡易テントです。
ロープを使って木と木の間に張たり、ストックを使って立たせたりします。
そのまま被って体を覆うことも出来ますよ。
着るタイプ
こちらは着るタイプのものです。
ザックを背負ったまま、着て歩くことも出来ます。
エマージェンシーシート
災害時にも使えるので、1枚は持っておきたいシートですね。
山座布団
お尻を地面につけると、とても冷えるので座布団があると良いです。
これは、普段の登山でも休憩時に使えるものなので、いつもザックに入れておくと良いですね
浄水器
もし近くに沢があれば、これで浄水して飲むことが出来ます。
水分補給が出来ない事は、体調を悪化させるので持っていると安心ですね。
道迷いについての知識
そもそも、道迷いをおこさないことが1番です。
もし迷ってしまった時、どうしたら良いのか知っているだけでも、気持ちが落ち着いて冷静な行動をとることが出来ます。
また登山届をしっかり出して知人にも伝えること、紙地図とコンパスとスマホアプリの地図を持つことなど。
コースタイムの短い低山だから、歩き慣れた山だから。
こんな気の緩みが、道迷いから遭難をおこす原因になってしまいます。
十分な計画と装備や持ち物をそろえて、山の勉強もして安全で楽しい登山を行って頂きたいです。^^




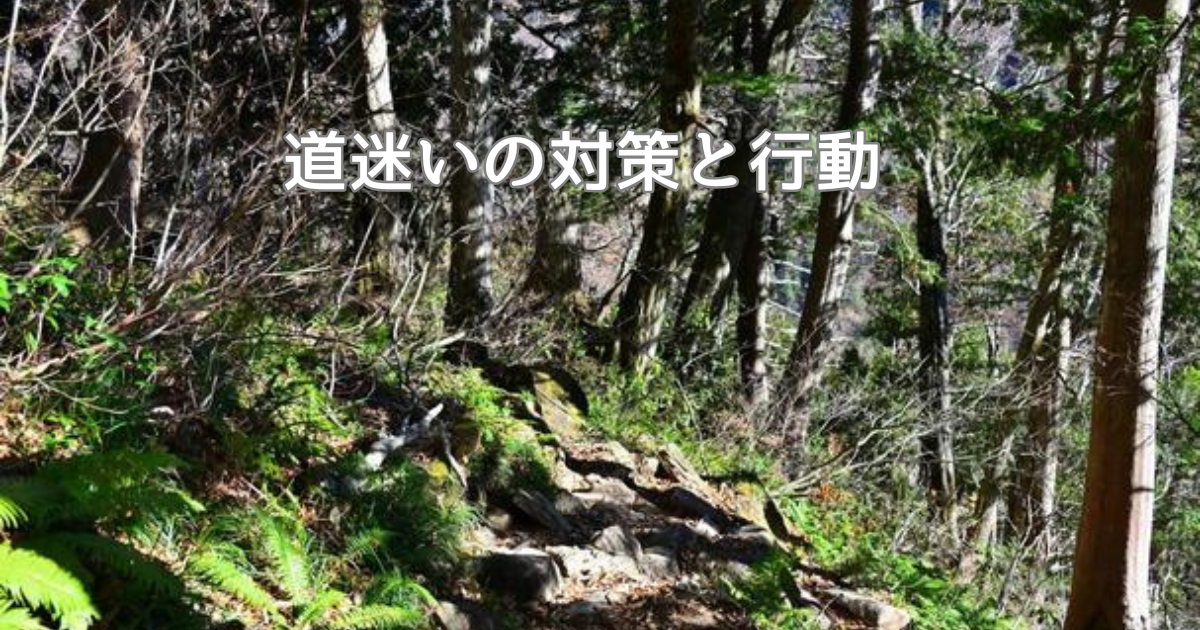
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18db8d92.229eae94.18db8d93.aa66a52e/?me_id=1191175&item_id=10034706&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmitsuyoshi%2Fcabinet%2Fregcp%2F03%2Fari00000000333.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/19874d78.7a9c118c.19874d79.24396824/?me_id=1277977&item_id=10010276&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-lodge-2%2Fcabinet%2Fari%2Fari-biv-solo.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/31f5bd5d.637310c7.31f5bd5e.79282e08/?me_id=1322293&item_id=10001353&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fecoride%2Fcabinet%2Fimg3%2Fsabage-129-03.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2ba8aa05.942c64c8.2ba8aa06.7cf13184/?me_id=1408771&item_id=10000137&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fworldwindshop%2Fcabinet%2Foutdoor%2Fo000000380.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3d8e12aa.2910f82f.3d8e12ab.2c77b71c/?me_id=1400780&item_id=10000061&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsakutto-couper%2Fcabinet%2F08393026%2Fimgrc0095499766.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

