山の歩き方を知ろう!
登山を始めたばかりの人は「登山って苦しいなぁ」って思っているかもですね。
嫌だなぁって思う前に、少しでも快適に楽しむためのコツを、知りたくありませんか?
山岳ガイドの平川さんが、YouTube動画で解説しています。
平川さんのレクチャーを元に、具体的なコツや方法を詳しく解説します
山の歩き方は靴の履き方から始まる
靴を履く時は、どのようにして履いていますか?
正しい履き方をマスターするだけでも、登山中の快適さが変わります
足を入れて紐を縛るまで
まず靴に足を入れたら、足首を直角に曲げて紐を持ち、靴を安定させた状態で踵をトントンと地面に着くようにします。
すると足の踵と靴の踵が、しっかりフィットするのです。
これを行うことで、足が靴の中で動くことを防ぎ、しっかり指を使って正しく歩けるのです。
足が靴の中で動くと、指先が押されて痛みが出たり、踵に靴ずれが出来てしまうんですよ。
なので、踵を合わせることは、とても重要なことなのです。
靴紐の結び方
足の踵を靴の踵に合わせたら、そのまま足首を直角を保っててください。
その状態で、靴ひもを締めていきます。
靴の先端に近い方から、渡っている紐に指を引っ掛けて引っ張るようにすると、靴幅の調節が出来ます。
この時に、あまりギューギューに締め過ぎないように注意してくださいね。
歩いている内に、足は少しむくんでくるので、ギューギューだと痛くなって来るからです。
靴の爪に引っ掛ける時
上の方まで適度に絞めて行ったら、最後は2~3か所の爪に引っ掛けるのですが、この時に紐を交差して上に引っ張るのでは無くて、下方向へ向かって引っ張るようにします。
また直角にした足首は、爪に引っ掛ける時はそのまま直角を保っていて、キュッと絞める時につま先を伸ばすようにします。
これをすることで、足首の所がしっかり締まって。下り坂を歩いても足が靴の中で動いて前に滑るという事を防いでくれます。
また爪に引っ掛ける時は、紐を上から引っ掛けるようにしましょう。


靴ひもの外れやほどけを防ぐ
上から掛ける事で、紐が交差して爪から外れにくくなると言う訳です。
蝶々結びをしたら、もう1回輪に通して絞めると解けにくくなりますよ。


山の歩き方とは足や靴だけでは無い
歩き方でしょう?何言ってるの?って思いますか?
歩くときの足先の使い方は、歩き方の記事で詳しく解説しているので、読んで頂きたいです。
快適に歩くためのウェアリング
歩き始めは涼しい位が丁度良い、と言う人がいます。
どうせ歩けば直ぐに暑くなるからという理由で、肌寒いのに薄着で歩き始めるんです。
でもこれは、間違いなんですよ。
筋肉を冷やすと動きが悪くなるので、怪我や故障をし易くなってしまうからです。
少し暑くなって来たと感じるまでは、ウインドブレーカー等の上着を着て歩いた方が良いんです。
登山は、着たり脱いだりを頻繁に行って、快適な状態を保つ必要があります。
ハッキリ言って面倒なのですが、筋肉を守り体を守り元気に歩き続ける為には、頻繁な脱ぎ着が必要なのです。
このことについては『登山の服装はレイヤリング・・・』の記事で説明しているので、合わせて読んでください。
大事な山の歩き方
登山に最適な歩くペースと言うのは、普通にお喋りをしながら歩ける速さです。
ハーハーゼーゼー言いながら歩くのは、体への負担が大きいし、体内の酸素不足を起こして、高山病になり易いのです。
歩くペースを見る
歩くペースを知る(最大心拍数)
自分の最大心拍数を知って、それを超えないように歩くのが、自分のペースになります。
最大心拍数の計算方法は、(220-年齢)X 0.75 = 最大心拍数 となっているので、計算してみてください。
例えば、45歳の人だったら、220-45=175 X 0.75 で 131.25 です
また55歳の人だったら、220-55=164 X 0.75=123 です。
当然ですが年齢が上がるほど、ゆっくり歩かなければ心肺への負担が大きくて疲れやすい、と言うことになりますね。
つまり逆に、心拍数が最大を超えない位のペースで歩けば、疲れ難いということなのです。
心拍数が計れる、アプリやスマートウォッチを持っていれば、心拍数が判りますが、無かった場合は普通にお喋りが出来るペース、を目安にしてください。
水分補給も山の歩き方
登山では、脱水症状を起こしやすいので、水分補給を適切に行う必要があります。
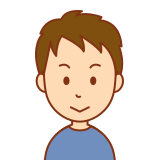
あまり汗をかかないからなぁ。
脱水なんて、ならないでしょう?
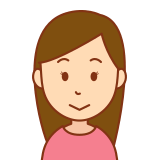
体内の水分は、呼気からも失われていきます。
また流れる汗をかかなくても、見えない汗(蒸気)は
出ているんですよ。
また少し汗ばむと、鼻水が出て来るってことは無いですか?
これは登山あるあるみたいで、多くの人が言っていますが、鼻水も水分ですよね。^^
どれくらいの飲めば良い?
まずは、自分がどれくらい脱水するかを計算します。
行動時間(h) X 体重(kg)X 5 =脱水量(ml)です。
体重60kgの人が、5時間歩いたとすると、5X60X5=1500ml という事になります。
これは脱水量ですが、飲む量は脱水量の7割必要、ということになっているので、1050mlは最低でも飲んでください、という事ですね。
この水分量をしっかり飲むことで、疲れ難く元気に最後まで歩けるという訳なんです。
普段、自分が飲んでいる水分量と比べてどうですか? 多いですか? 少ないですか? ^^
これだけじゃ足りない!
でも私は、この計算に不満を感じています。
それは、天気や気温の事が含まれていないからです。
天気が良くて暑い日と、寒くて天気が悪い日では、脱水量は大きく変わりますよね。
また、登山道のキツさも、大きく影響するでしょう。
お喋り出来る位のペースでと言っても、やっぱり急登を歩けばゆっくりでも息が切れます。
クソ暑い(失礼w)日で、ダラダラ汗をかいていたら、どうですか??
なので、上で計算した水分量は、最低でも必要な量と考えてくださいね。
これだけ有れば良い、では無いですよ!
山の歩き方は着く前から始まっている
登山口へ着くまでの間に、水分を500mlとエネルギーとなる物を何か食べておく、とバテにくいと言われています。
これは、私の体験からも間違いないと、確信しています
移動時間に準備を始める
家で食事して登山口へ着くまでに、食べた食事のエネルギーは、かなり消費されてしまっています。
水分も同じで、途中でトイレに寄ったりお喋りで呼気から失われたり、汗をかいたり・・・
なので、登山を始める準備として、登山口に着く30分くらい前までに、水分を500mlと少しの食べ物、を摂取しておくのが良いという訳なんです。
私のしていること
私はいつも主人が運転する車で、登山口まで向かいます。
主人が「あと30分位で駐車場に着くよ」って言ってくれるので、そしたらお握りかアンパンを1個食べます。
私的には、お握りよりアンパンの方がが、効率的だと感じていますけどね。
水分は家を出て直ぐから、チョクチョク飲んでいます。
実際にあったこと
たまたま登山口が家から近いところで、30分も経たない内に着いた時、全く何
も食べたい気分では無かったので、食べずに歩き始めました。
そしたら30分も歩かない内に、体が怠くて重くなってきちゃったんです。
これは『シャリバテ』の症状です。
特におすすめアミノ酸
アミノ酸はたんぱく質で、たんぱく質は筋肉の元ですよね。
元気に筋肉が働く為に、また筋肉を壊すこと無く歩き続ける為に、登山前・登山中にアミノ酸を摂取するのが望ましいです。
アミノ酸については『安全で快適な登山を楽しむために・・・』の記事で解説し、製品の紹介もしています。
またアミノ酸を摂る時には、水分補給の役目も果たしてくれるので、サプリメントでは無くてゼリー飲料がおすすめです。(看護師さんからの話しです)
こういう物です。⇩ 下のものは1個が45gだから、気にするほどの重さじゃないのが良いですね
山の歩き方、行動食の必要性
食べた物がエネルギーに替わるのは、3~4時間過ぎてからです。
そしてエネルギーとしての持続時間は、お握り1個で1時間から1時間半と言われています。
なので休憩する度に、ナッツ・チョコ・羊羹などなどで、エネルギーを補給する必要があるのです。
登山口に入ったら、山頂でのご飯まで何も食べない、と言うのではパフォーマンスが激落ちしちゃうし、シャリバテ(低血糖)も起こします。
なので、一口ずつでも良いからチョクチョク食べる、ようにしましょう。
山の歩き方では身体全てを考える
登山は、登山口に着く前から始まります。
そして靴の履き方も、パフォーマンスに大きく影響するのです。
また快適に歩き続ける為には、水分補給とエネルギー補給が大事。
歩くスピードも、普通にお喋りが出来るくらいの速さで。
ウェアは、着たり脱いだりの、レイヤリングが必要です
山の歩き方はトータルで考える
水分補給はお茶やお水だけ、となると体液が薄まってしまうので、出来ればスポーツドリンクを飲むようにしましょう。
トロミや甘味が嫌い!という人は、自宅で水に塩少々と砂糖少々(+レモン汁)が、スポーツドリンクの代わりになるそうですよ。
私もスポーツドリンクの味が苦手なので、蜂蜜レモンを作って持って行くことが多いです。
そして、塩分補給には梅干しを食べたり、塩飴を舐めたりしています。
それぞれの好みに合わせて、飲み物や行動食を工夫して下山まで、元気に楽しい登山が出来るようにしましょうねぇ。
最初は何が良いか、分かりにくいと思うので色々と持って行って、自分に合うものを見つけてくださいね。




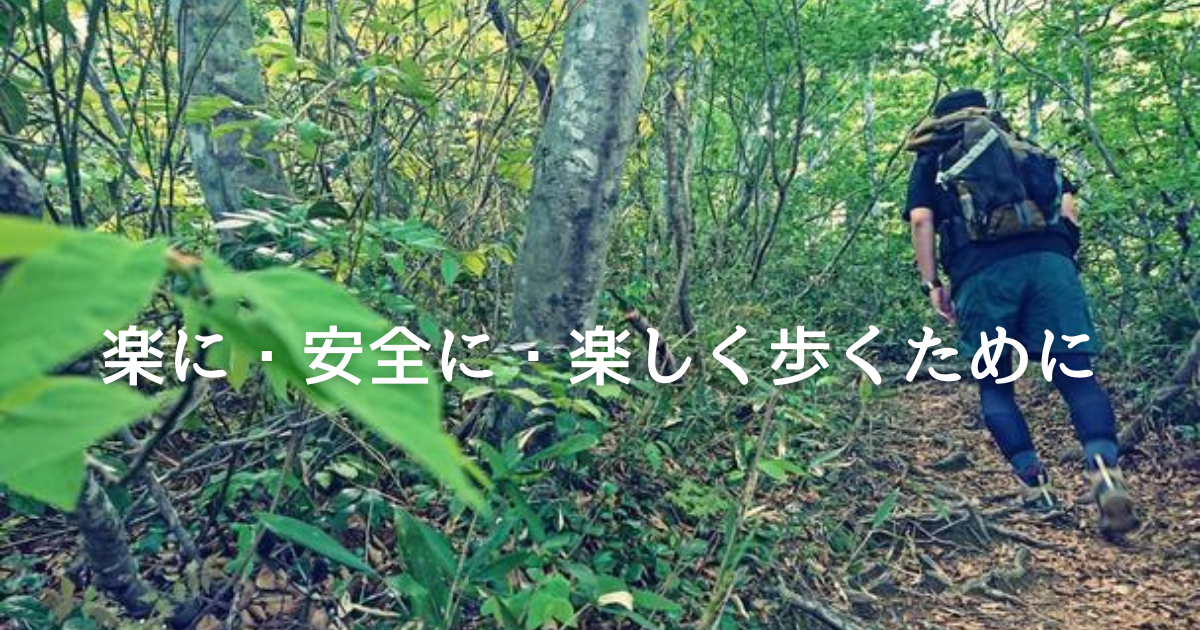
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3caa34be.b10c780c.3caa34bf.5dd3c64c/?me_id=1340644&item_id=10000014&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fcoreplus1%2Fcabinet%2Fgel%2F10096994%2Fimgrc0084560036.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


コメント